報告レポート:政治経済学部【公開講演会】2021「コロナ危機からその先へー生活保障をどう考えるかー」
報告レポート:11/24「コロナ危機からその先へー生活保障をどう考えるかー」
2021年11月29日更新
政治経済学部【公開講演会】2021では、「ポストコロナ時代を導く視点を求めて─地球環境、困窮する生活者、オンライン化に潜む陥穽を考える─」をテーマとしたシリーズ講演を全3回で実施します。2回目の11月24日は『コロナ危機からその先へー生活保障をどう考えるかー』として、コロナ禍が私たちの社会に与えた影響について、社会保障と財政の問題を中心に、埼玉大学人文社会科学研究科准教授 高端正幸先生にお話しいただきました。
*本公開講演会はアセンブリアワーという聖学院大学の特色ある教育プログラムの中で行われるもので、政治経済学部を中心に多くの学生が事前学習を経て参加。一般の方にも公開しています。今回は会場とオンライン配信のハイブリッド形式で実施しました。

【概要】

コロナ危機からその先へー生活保障をどう考えるかー
講師:高端正幸先生(埼玉大学人文社会科学研究科 准教授)
- 日時 2021年11月24日(水)10:40〜12:10
- 場所 聖学院大学チャペル
- 開会の言葉 政治経済学部長 高橋愛子
- 開会挨拶 聖学院大学学長 清水正之
- 講師紹介 政治経済学部准教授 長嶋佐央里
- 閉会の言葉 政治経済学部長 高橋愛子
(コーディネーター)
政治経済学部 准教授 長嶋佐央里/政治経済学部 准教授 柴田怜
【講演内容】*レジュメより抜粋
コロナ禍が私たちの社会に与えた影響を掘り下げてみると、
①どう「いま」を捉えることができ、
②そこからいかなる「これから」の課題を汲み取ることができるのか
について、社会保障と財政の問題を中心におきつつ、少し広い視野を持って整理してみたい
- コロナが収束し、「元の日常」に戻れれば良いのか?
- コロナ禍は不平等に私たちを襲った
- 所得階層に張り付いた多様な不平等
- 必要な所得が公的に保障されない
- 「元の日常」=自己責任型社会に生きる私たち
- ニーズを満たすということ:財政学の観点
- ニーズを満たすためにお金がかかる日本
- 自己責任型社会の生きづらさ
- そもそも自己責任型社会は無理筋である
- 経済成長より、ニーズの充足に資源を振り向ける
- 「戻るに値する日常」を創り出すためにー「公助」はニーズを満たせるかー
- 「公助」の枯渇 ①担い手
- 「公助」の枯渇 ②財源
- 止まらない「公助」の後退
- コロナ禍は「つながり」の大切さに気づかせたが、、、
- 「戻るに値する日常」を「私たち」は希求できるのか
- 私たちの抱く自己責任意識
- 以上のデータが物語ること
- 進む危機の顕在化と芽生える意識の変化
- しかし「共同の財布」を税で満たすことが拒否される
- 「公助」を妨げる政府への不信
- 「公助」と「共助」を妨げる他者への不信
- しかし「不信」が「問題意識」につながりにくい
- それでもコロナ禍で変わる私たちの意識
- おわりに
共同性を再編・拡充し、ニーズ充足の危機を乗り越えることは可能か? - 質疑応答
講演を通して、いつの間にか当たり前と思い込んでいた自己責任感やコロナ危機によってあぶり出された問題など、普段目にすることができない国際データを示していただき、データをもとに新たな視点で日本の状況を知ることができました。
これからをどう生きていくのか、そして自分だけが生きていくと考えるのではない本当に生きやすい社会の仕組みに直接結びつく、財政や税のことを考える機会をいただきました。
質疑応答では、「難しいのかもしれないが、どのようにしたら今の日本の社会で増税ができるのか?」など、学生より質問があがりました。
当日の様子(写真)

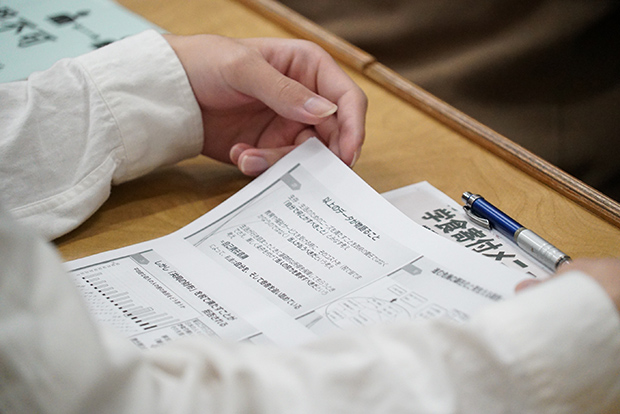

次回の政治経済学部【公開講演会】2021
- 〈インターネット〉〈表現の自由〉〈ヘイトスピーチ〉
日時:2022/1/12(水) 10:40-12:10
場所:聖学院大学チャペル
講師 宮下萌弁護士