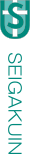MY THEME
髙田 若郡さん
で自分の好きなことに
確信がもてるようになりました。
子どもが好き × 英語
で欧米文化学科を選びました
中学生の時に授業を通じて世界のことを教えてくれる英語の先生に出会い、英語にとても興味をもちました。加えてもともと小さい子どもが好きだったので、高校生の時、子どもに英語を教える分野に進みたいと思っていました。その話を母にしたところ、聖学院大学のことを知っている母の友人が、欧米文化学科のことを教えてくれました。英語に興味をもったきっかけが世界を知ることだったので、日本と海外の違いや世界の文化に触れる欧米文化学科の学びは魅力的で、少人数制も私には合っていると感じました。欧米文化学科にはJ-SHINEという児童英語教育の資格をとれる専門のプログラムがあり、児童英語の第一線で活躍する先生が揃っています。オープンキャンパスに参加してそのことを知り、聖学院大学に進学しようと決めました。
学外での学びが、
教えることの喜びを教えてくれた
J-SHINEの資格を取得するためのカリキュラムのひとつに「児童英語教育(インターンシップⅠ・Ⅱ)」という校外学習があります。提携している小学校で、小学1~2年生を対象に、大学4年生が実際の英語の授業を行い、大学3年生はサポートという形で参加します。私は当時3年生だったのでサポート側で参加したのですが、それでもとても楽しかったです。児童英語は中学校からの英語の授業と異なり、文法や日本語での意味は一切教えません。イラストやジェスチャーで英語は英語のままとして教えていきます。歌ったり踊ったり体を使った教育法も取り入れます。小学生は素直な分、教えたことをそのまま覚えてくれるため、次に会った時にはもう定着がみられ、やりがいを感じました。
他にも大学で紹介してもらった荒川区主催の「英語キャンプ」というイベントに参加したことがありました。このイベントは小学校高学年対象で、その時は自分が英語を直接教える立場でした。ここでも同じように子どもたちはすぐに英語を身につけていき、教えることの喜びを感じました。「児童英語教育(インターンシップⅠ・Ⅱ)」も「英語キャンプ」も、講義で習った理論が本当に教育現場で実践され、実際に効果的に機能しているのを目の当たりにして「講義で先生に教わったことはこれか!」と感動しました。
不安な時には、いつも支えてくれる先生がいる
今年は「児童英語教育(インターンシップⅠ・Ⅱ)」で自分が主体となって教える側になります。昨年は活気があってとても楽しいクラスでしたが、今年、私が担当するクラスがそうとは限りません。不安はありますが、そのような時はゼミの東先生に相談にのってもらいます。東先生は児童英語教育の第一人者であり、受験する時からお世話になっている先生です。どのような時でも私に必要なアドバイスを的確にくれるだけではなく、先生が自ら調べて安心できる材料を用意してくれます。とはいえ全て答えを出すのではなく、最後は自分で答えを見つけて、私が成長できるようサポートしてくれています。東先生に限らず聖学院大学は全体的にそのような面倒見の良さを感じます。どの先生も学生がやりたいことに寄り添いアイディアを出して選択肢を広げてくれます。先生たちは近すぎず、遠すぎない距離感で見守り、何か困るとちゃんと支えてくれ、学生の主体性を尊重してくれます。だから自分が興味あることに専念できるのだと思います。
学内外の学びを通して
将来の進路に広がりが出た
将来はどんな形であれ小さい子どもに英語を教える仕事に携わりたいと思っています。聖学院大学に入って、英語の先生以外にも選択肢があることを知りました。英語の知育玩具や知育アプリにも児童英語教育の力は生かせるかもしれません。今は絵本の出版にも興味があります。児童英語という点を重視して就職活動を進めていきたいと思っています。