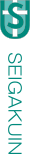MY THEME
木村 鈴菜さん
私も一人ひとりを支える
教員になりたい
子どもたちを支える存在になりたい
教員を目指したきっかけは小学校5・6年生の時の担任の先生でした。ある日、先生は私に「学級委員やってみない?」と声をかけてくれました。内向的なタイプだった私には、とても務まる気がしなかったのですが、周りの友だちの勧めもあって結局半年間学級委員をやりました。この半年間を通して、私は不思議と人と関わることが好きになっていきました。今思うと先生は私のことをちゃんと見ていて、人と関わることが本当は好きなのではないかと声をかけてくれたのだと思います。先生に変わるきっかけをもらったと、とても感謝しています。そして私も先生のようになりたいと小学校の教員を目指すようになりました。
社会に即した学びと、現場での経験、
両面から成長できる
大学も教員になることを前提に選び、小学校教諭一種と特別支援学校教諭一種の2つが取得できるという理由で聖学院大学を受験しました。聖学院大学の教職の授業で印象深かったのは「教職演習F」です。その授業のテーマの一つにインクルーシブ教育がありました。障がいで区別せず、多様性として受け入れ、みんな同じ場で学んでいくという考え方です。この授業を通して、勉強が苦手な子がいたら、その子のための課題を用意したり、どうやって学級のみんなと学んでいくかを考え、誰一人取り残さない教育をしていくことが大事であると学びました。
また聖学院大学には「学校インターンシップ」という制度があります。大学の隣にある聖学院みどり幼稚園に行き、幼児教育の現場を見学するプログラムです。教育実習より早い時期に行われ、ただ見学するのではなく、子どもの様子をしっかり観察し、それに対する先生の関わりを学ぶことが目的です。実際、子どもを観察しているといろんなことが見えてきます。例えば一人で遊んでいる子どもは、仕方なく一人で遊んでいるのではなく自ら一人で遊ぶことを選んでいる場面があります。そういう観察を通して、この子の行動の背景には何があるのかなと考える視点が身につきました。座学で学んだことを、体験を通して自分の中に落とし込むことができました。
勉強も悩みも、最後までしっかりサポート
成長を実感しながらも自信をなくすこともよくあります。私の場合は他の職業を全く考えていなかったので、もし教員になることに挫折したらどうしようとか、自分にクラスの子どもたち全員を見られるだろうかなど不安になりがちです。そもそも勉強が得意ではありません。そんな時に支えてくれるのが学科の先生方と「教職支援センター」の先生方です。「教職支援センター」は教職免許の取得で終わらず、教員採用試験に向けて、勉強の仕方や情報提供、相談などサポートしてくれる部署です。不安を打ち明けると、話を聞いてくれて「最初からうまくいく先生なんてまずいない」「他の学生も同じ気持ちで悩んでるから一人じゃないよ」と励ましてくれます。本気で最後の最後まで私のことを支えようという気持ちが伝わってきて、とても安心感があります。
大学全体で一人ひとりの成長に
ちゃんと寄り添う
「教育的愛情」という言葉があります。私はこの言葉を、障がいがあったり他の子と関わりがうまく持てない子どもでも平等に関わり一緒に学んでいくことだと捉えています。それは一人ひとりと向き合うことでもあります。聖学院大学はまさにそういう大学です。過去に授業を受けたことのある先生も私の近況を知っていて、廊下で会うと話しかけてくれます。私だけではなく他の学生に対しても同じように気にかけてくれています。
入学前は、この大学で教員になれるのだろうかと思っていました。しかし今は聖学院大学で良かったと思っています。この大学で学んだ私の目標は、子ども一人ひとりをちゃんと愛して寄り添える先生になることです。