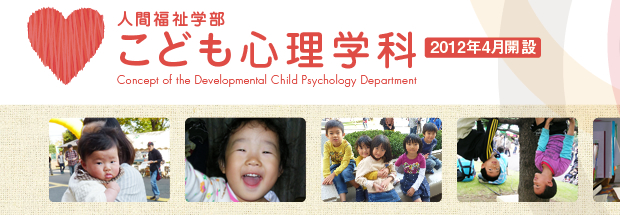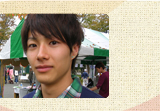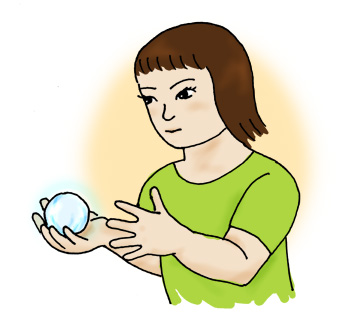
昔、昔の話である。教育的ニーズのあるお子さんへの心理・教育を学ぶために入学した大学院では、指導教官の研究室に大学院生それぞれが机をもらった。インスンタント大家族みたいなものだったかもしれない。インスタント家族メンバーと寝食をともにする生活をそれから何年にも渡ってすることになった。一緒に学ぶ仲間と先生、常に誰かしらいる空間で私の時間が流れていった。
研究会で議論し合う、個人的に論文指導を受ける、セッション(子どもたちへの指導)の準備を仲間と一緒にする、時には、朝方までお酒を片手に雑談を繰り広げる。
今、振り返ってみるとその時間が、たまらなく懐かしくなるのはなぜだろうか。
いつだったか先生がエドワード・セガンの言葉を教えてくれた。
「彼等の視覚、聴覚、その他の感覚を発達させるのと同じく、彼等の愛情の感覚を発達させるには、新しい道具や新しい教師が必要なのではない。必要なのは、彼等の感じる力にまで、愛情をとどかせてやることなのである。自分は愛されているのだと、その子どもに感じさせ、次には、熱心に人を愛させる、ということがわれわれの教育の初めであり終わりなのである」(エドワード・セガン『障害児の治療と教育』pp.207)
それから多くの時間が流れて行ったけれども、折あるごとに口ずさみながら、自分を戒めるように、今をともに生きるこどもたちや学生さんたちに向き合う。
久々にいただいた先生のメールには、先のエドワード・セガンの言葉とともに先生自身の思いが添えられていた
「この言葉を読むと、人と人がどう向き合うのかということが、ひとりの人を育んでいくんだということに気づかされます。知的障害をもつ人達に愛情を持って接し続けることが,ともに新しい文化を作り出すことになるのだと,最近,思っております」
嬉しかった。インスタント大家族は、きっと時間と場所が離れても、それぞれの心に蓄積された温かい記憶でつながっている。そして、その記憶は、未来へ向かう人間の希望となるのだろうと思う。
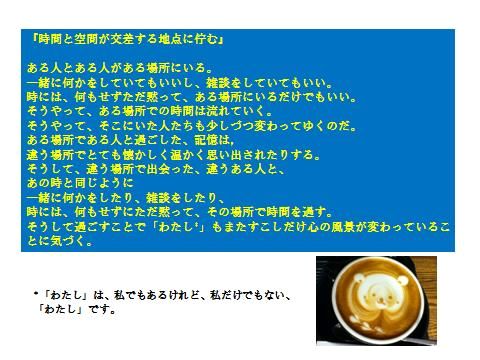
「今を生きる」ピーター・ウィアー監督作品 DVD
エドワード・セガン著 末川博監訳(1983)「障害児の治療と教育」ミネルヴァ書房
> 教員リレーエッセイ一覧に戻る