AH報告レポート:児童学科30周年記念 AH連続講座「⼦どもの本をつくるひとたち」
報告レポート
2022年10月18日更新
児童学科30周年記念 AH連続講座 子どもと教育
~子どもとつながるさまざまな世界~
第3回「⼦どもの本をつくるひとたち」荻原華林⽒
2022年10月5日のアセンブリアワーにて児童学科30周年記念 AH連続講座 子どもと教育 ~子どもとつながるさまざまな世界~ 第3回「⼦どもの本をつくるひとたち」が行われました。
この講演では児童文学を発刊している静山社で編集者として働いている荻原華林氏を講師にお招きして、児童文学ならではの編集者の仕事についてお話いただきました。
荻原氏はこれまでにハリーポッターシリーズの文庫本をはじめ、『ぼくらの七日間戦争』で有名な宗田理さんの『悪ガキ7』シリーズや、魔法で物と記憶を預かる『十年屋』シリーズなど多数の人気のある児童文学を手がけられました。
今回の講演では宗田先生の『悪ガキ7』シリーズを例に、一冊の本ができるまでの様々な工程を具体的なエピソードを交えてわかりやすく説明いただきました。
当日は学生や教職員だけでなく一般の方も会場に足を運び、およそ40名の参加者が荻原さんの話に耳を傾け、また質疑応答でも多くの質問が挙がりました。
荻原氏は編集者の仕事を「一人でなにかできるということではなく、作家やイラストレイター、デザイナー、校正者など様々な方と連携して成り立つ仕事。」と言います。
また、児童書を作成する際の注意点や大人向けの一般図書とは異なる点を挙げ、自身が思う子どもの本づくりに欠かせないポイントを述べられました。
最後に、編集者や出版業界を目指す学生たちに向けて「すぐに希望通りの職に就けるとは限らないが、何故自分がその仕事に就きたいのかを考えてみると、選択肢が広がるかもしれない。人生には横道が多くあり、いつその道が開け、どこに繋がっているかわからない。」とのメッセージを伝えました。
当日の様子

子どもの世界を理解し子どもの意を汲んで関わる力を養う~学科の学び
子どもの世界を理解し個性を育てる能力をつける
---2023年4月より、児童学科は「子ども教育学科」に名称変更予定
現代社会において、子ども一人一人を育む関わりには高度な専門性が求められます。同学科では、子どもの言葉、表現、心理などを理解することを学びの第一歩とし、子どもの世界を理解し子どもの意を汲んで関わる力を養います。また、保育・教育職を希望する学生のためには、専従スタッフがいる教職支援センター・実習準備室があり、授業の他にも、資格・免許状取得から採用試験対策まで支援します。子どもの意思を汲む力は、言葉を大切にしながら言葉をこえて他者と通じ合う力も育み、どのような職種のどのような企業にも通用します。卒業後の進路は、多様な職種に広がっています。
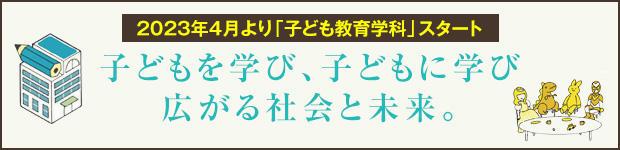
関連情報はこちら
-
【授業紹介】Smile English(幼児の英語)
子ども教育学科の授業を紹介するリレーコラムです。
- 2023年4月より、「児童学科」は「子ども教育学科」に名称変更予定
- キャンパスレポート Campus Report TOP